AD可溶有機物は比較的分解し易い有機物なので、COD(化学的酸素要求量)の測定と同様な手法で測定可能である。そこで、COD測定に用いられている酸性過マンガン酸カリウム法を改変した手法で測定する。
必要な器具
必要な試薬・器具
- 濃硫酸、市販品の0.02mol/L過マンガン酸カリウム溶液
(代用可 市販品の10%硫酸、市販品の0.04mol/L過マンガン酸カリウム溶液)

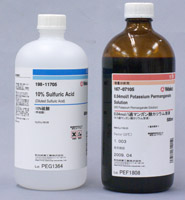
滴定値は反応液中の硫酸濃度、過マンガン酸カリウム濃度により大きな影響を受ける。従って、この手法では濃度等のアレンジは厳禁である。硫酸は濃硫酸を希釈した約18.8%硫酸か、市販品の10%硫酸を使用する。それぞれで使用する過マンガン酸カリウム溶液の濃度が異なるので、注意が必要である。
濃硫酸を使う場合、脱塩水100±1gに濃硫酸24.47g(24.45〜24.50g) を加えて約18.8%硫酸を調整する。劇薬なので必ず手袋を着用し、耐薬品性の高いガラス製の器具を使って加える。必ず脱塩水を先に取り、そこに濃硫酸を加える。濃硫酸を加えると熱くなるので、冷めるのを待ってから試料に加える。熱で水分が蒸発して濃度がやや変わるが、気になる場合は放冷前後の重量から蒸発した水分量を計算して加える。
希釈に使う水は、可能なら脱塩水あるいは蒸留水を使う。入手が困難な場合は、ドラッグストアのベビー用品コーナーにある調乳用の水(ミネラル分を除去した水)を使う。それも入手困難な場合は、市販品のミネラルウォーターを用いる。水道水を用いても測定値に大きな誤差は生じないと考えられるが、できれば使用しない。
| 脱塩水・蒸留水 | 市販品の調乳用の水 | 市販品のペットボトル入り ミネラルウォーター | 水道水 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | △ |
- グルコース
- 1Lビーカ(代用可 ポリビーカ・オイルポット)
- 秤(2kg程度まで測定できるもの)
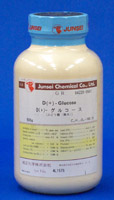



滴定値は、硫酸濃度、加熱時間等によりずれてしまうことがある。そのため、できればグルコースを脱塩水に溶かして標準液を作成し、滴定値を補正する。なお、補正しなかった場合、誤差を考慮して推定AD可溶有機物量200mg/g(乾物)以上の試料についてAD可溶窒素の測定を行う。従って、測定が必要な試料の点数が多くなる。
グルコース0.30gを脱塩水1000±1gに溶かし、0.3g/Lグルコース溶液を作成する。これを0.2AD液と供に希釈して標準液とする。調整に使う水は、18.8%硫酸の調整に準ずる。
- 秤
- ビーカ(代用可 紙コップ)
- 駒込ピペット




- ピペッター(容量200〜1000μL)[推奨](代用可 駒込ピペット等+秤)
- ガラス製試験管(5〜10mL程度、透明)
- 試験管立て



- ガスコンロ
- 圧力鍋(直径18〜22cm)


|
・タイマー |

|
- 洗い桶
- 市販品の0.05mol/L シュウ酸ナトリウム溶液
- 市販品の0.005mol/L過マンガン酸カリウム溶液

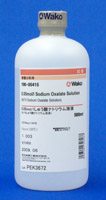
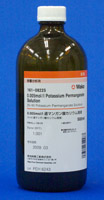
- パスツールピペット(代用可 駒込ピペット等)


滴定は過マンガン酸カリウム溶液を一滴ずつ加える必要がある。駒込ピペット等を使う場合は、きちんと一滴ずつ加えることができ、一滴の量があまり多くないもの(口が小さいもの)を選ぶ。
過マンガン酸カリウム溶液は2種類必要である。状況に応じ、より高濃度の溶液を希釈使用しても良い。ただし希釈は正確に行うこと。固体の試薬を溶かして作成することも可能だが、正確に作製する手順は煩雑なので勧めない(作製方法はCODの測定手法を記した実験書を参照すること。粉末の試薬からのシュウ酸ナトリウム溶液の調整も同様)。なお、市販品の過マンガン酸カリウム溶液の使用期限は半年、シュウ酸ナトリウム溶液の使用期限は1年である。
あった方が良い物品
- 厚手のゴム手袋
- 軍手
- 温度計
- 白紙(A4サイズ程度)
- 重曹(廃液中和用)


手順
希釈
0.2AD液自体も過マンガン酸カリウムと反応するため、抽出に使った0.2AD液も抽出液と同様に滴定する。滴定に先だって抽出液を希釈するが、0.2AD液も同様に希釈する。同時に0.3g/Lグルコース溶液を希釈し、グルコース標準液を調整する。希釈倍率は、18.8%硫酸を使う場合は20倍、10%硫酸を使う場合は10倍である。
希釈に使う水は18.8%硫酸の調整に準ずる。なお、水道水を使う場合は、一度に測定する試料全てを同じ時に取った水道水で希釈する。
分取する0.2AD液、抽出液の量が少なく、粘性が高いので、希釈は秤で重量を見ながら行なう。
秤にビーカ、紙コップ等の希釈用容器を載せ、ゼロセットする
↓
抽出液(0.2AD液)を1.03±0.01g分取する
↓
秤をゼロセットする
↓
希釈用の水を18.95〜19.05g加える
↓ ・10%硫酸の場合は希釈用の水8.95〜9.05gを加える
ガラス棒等でよく撹拌する
同様に、グルコース標準液を調整する。グルコース標準液には、0.2AD液を加える。
秤にビーカ、紙コップ等の希釈用容器を載せ、ゼロセットする
↓
0.2AD液を1.03±0.01g分取する
↓
秤をゼロセットする
↓
0.3g/Lグルコース溶液を8.95〜9.05g加える
↓
希釈用の水を9.95〜10.05g加える
↓ ・10%硫酸の場合は希釈用の水を加えない
ガラス棒等でよく撹拌する
なお、ここで調整したグルコース標準液は、常温で3ヶ月程度保存可能である。ただし、水道水を使って希釈した場合は水道水の成分が変わる可能性があるため、使い廻さない。
反応・滴定
このように調整した希釈液を、硫酸、過マンガン酸カリウム溶液と混合し、反応液とする。反応液の調整は、分取回数が多いため、ピペッターの使用を推奨する。
18.8%硫酸を使う場合:
- 20倍希釈抽出液1.0±0.01mL(g)
- 18.8%硫酸 1.0±0.01mL(1.14±0.01g)
- 0.02mol/L過マンガン酸カリウム溶液1.0±0.01mL(g)
10%硫酸をを使う場合:
- 10倍希釈抽出液 0.5±0.01mL(g)
- 10%硫酸 2.0±0.02mL(2.14±0.02g)
- 0.04mol/L過マンガン酸カリウム溶液 0.5±0.01mL(g)
なお、滴定結果がばらつく場合があるので、2連(0.2AD液は3連)で測定する。
試験管に希釈抽出液、希釈0.2AD液、グルコース標準液を分取する
↓
試験管に硫酸を加え、振り混ぜる
↓
鍋をコンロにかけ、水を沸騰させておく
↓ ・湯は試験の液面より少し上くらいまでで十分
試験管に過マンガン酸カリウム溶液を加え、振り混ぜる
↓
沸騰水中に試験管を試験管立てごと入れ、8分間加熱する
↓ ・過マンガン酸カリウム溶液を加えたら、できるだけ速やかに湯浴する
洗い桶に冷水を入れておく
↓
8分後に試験管立てを取り出し、冷水に浸す
コンロの火を消す(湯は捨てない)
↓ ・熱いので軍手の上に厚手のゴム手袋をして試験管立ての出し入れを行う
試験管が十分冷えたら、試験管立てを冷水から取り出す
↓ ・冷水は捨ててよい
試験管に0.05mol/Lシュウ酸ナトリウム溶液
0.85±0.02mL(g)を加え、振り混ぜる
↓
全ての試験管に溶液を入れ終わったら、試験管立てごと鍋(湯温70〜85℃)に入れる
・湯の温度を確認し、90℃を超えていたら85℃くらいになるまで待つか、
↓ 水を加えて冷ます
試験管中の沈殿物等が溶けて透明になるまで待つ
↓ ・溶けにくい試料では試験管を取り出して振り混ぜる
試験管を一本取り出して水滴を拭く
↓
秤の上にビーカを載せ、そこに試験管を置いてゼロセットする
・ビーカは試験管を置くため。試験管が倒れなければ他の容器でも良い

 ↓
試験管を手に持ち、パスツールピペット等で
0.005mol/L過マンガン酸カリウム溶液を一滴ずつ入れて振る
↓ ・過マンガン酸カリウムの色はすぐに消えて透明になる
過マンガン酸カリウムの色が消えにくくなったら、様子を見ながら少しずつ入れて振る
↓ ・白紙を背景にすると着色が分かり易い
過マンガン酸カリウムの色が消えずに、溶液が薄いピンク色に着色したら滴定終了
↓
試験管を手に持ち、パスツールピペット等で
0.005mol/L過マンガン酸カリウム溶液を一滴ずつ入れて振る
↓ ・過マンガン酸カリウムの色はすぐに消えて透明になる
過マンガン酸カリウムの色が消えにくくなったら、様子を見ながら少しずつ入れて振る
↓ ・白紙を背景にすると着色が分かり易い
過マンガン酸カリウムの色が消えずに、溶液が薄いピンク色に着色したら滴定終了
 ↓
試験管を秤の上のビーカに載せ、滴定に使った過マンガン酸カリウムの重量を測定し記録する
↓ ・試験管を載せる前にゼロセットしてはいけない
次の試験管を取り出して水滴を拭く
・湯の温度を確認し、60℃を切ったら1〜2分程度コンロに火をつけて加熱する。
↓ 温度が80℃を越えないように気をつける。
秤の上のビーカに試験管を置いてゼロセットする
・同様の滴定操作を最後のサンプルまで行う
↓
試験管を秤の上のビーカに載せ、滴定に使った過マンガン酸カリウムの重量を測定し記録する
↓ ・試験管を載せる前にゼロセットしてはいけない
次の試験管を取り出して水滴を拭く
・湯の温度を確認し、60℃を切ったら1〜2分程度コンロに火をつけて加熱する。
↓ 温度が80℃を越えないように気をつける。
秤の上のビーカに試験管を置いてゼロセットする
・同様の滴定操作を最後のサンプルまで行う
滴定後の溶液は、マンガン含量が300mg/L程度であり、水質汚濁防止法の排出基準10mg/Lを上回る。重金属廃液として、業者に処分を委託する。
使っている試薬により変わるが、0.2AD液の滴定値は 0.3〜0.4g、グルコース標準液の滴定値は 1.0〜1.1g、抽出液の滴定値はその間に入ることが多い。
換算
滴定値は平均を取り下の数式でAD可溶有機物量に換算する。なお、「5. 分析値の利用」では表計算ソフトを使いこの計算をする。
グルコース標準液による補正を行う場合:
推定AD可溶有機物量(mg/g・乾物)
= 1.226 x ((抽出液滴定値 − ブランク滴定値) ÷ 0.05)
x ((150 ÷ (試料重量(g)x 乾物率(%)÷ 100)) ÷ (1000 x
(グルコーススタンダード滴定値 − ブランク滴定値) ÷ 135))
= 496.53 x ((抽出液滴定値 − ブランク滴定値)
÷ (グルコース標準液滴定値 − ブランク滴定値))
÷ (試料重量(g)x 乾物率(%)÷ 100)
この値が230以上の場合、AD可溶窒素の測定を行う。
補正を行わない場合:
推定AD可溶有機物量(mg/g・乾物)
= 0.26 x ((抽出液滴定値 − ブランク滴定値) ÷ 0.05) x 150
÷ (試料重量(g)x 乾物率(%)÷ 100)
= 780 x ((抽出液滴定値 − ブランク滴定値)
÷ (試料重量(g)x 乾物率(%)÷ 100)
この値が200以上の場合、AD可溶窒素の測定を行う。
※AD可溶窒素測定の基準値の設定について
AD可溶窒素測定の基準値はAD可溶有機物量250mg/g(乾物)であるが、測定誤差が大きい手法の推定値では、250より低くしている。
正しいAD可溶有機物量が250mg/g(乾物)以下なのに推定値が250以上になった場合、AD可溶窒素を測定して緩効性窒素を計算しても、無視して良いくらいの数値になる。
しかし、逆の場合、AD可溶窒素を測定しないので、本来考慮しなければいけない緩効性窒素をないものとして扱ってしまう。その危険性を少しでも減らすために、基準値を低く設定している。
目次
- 1. 試料の準備と水分量・粗灰分
- (1) 試料の準備
- (2) 水分(乾物率)
- (3) 粗灰分(通常不要)
- 2. RQフレックスの使い方
- 3. 無機成分分析
(速効性肥料成分) - (1) 0.5M塩酸抽出
- (2) 塩酸抽出液の希釈
- (3) アンモニアの測定
- (4) 硝酸の測定
- (5) リン酸の測定
- (6) カリウムの測定
- (7) カルシウムの測定
- (8) マグネシウムの測定
- (9) 堆肥中の成分量の算出
- 4. 簡易デタージェント分析
(緩効性窒素) - (1) 手順の概略
- (2) 0.2AD液での抽出処理
- (3) AD可溶有機物量の簡易推定
(パックテスト) - (4) AD可溶有機物量の簡易測定
(過マンガン酸カリウム滴定) - (5) AD可溶窒素の測定
- (6) 近赤外分光法によるAD可
溶有機物・AD可溶窒素の推定 - 5. 分析値の利用