平成28年度イベント報告
(一社)ぎふクリーン農業研究センターとの分析法研修を行いました(2月20、27日)
(一社)ぎふクリーン農業研究センターでは、土壌分析や残留農薬分析の業務を行なっています。農業技術センターと技術交流を進める中で、今後の取り組み可能な分析項目を探るため「土壌の可給態窒素簡易・迅速評価法」と「堆肥の肥料成分の簡易分析法」の研修を行いました。研修では従来法と簡易法の違いを理解していただくとともに、現有機器での実施の可能性についても議論を行いました。簡易分析の手法については取り組みやすいと好感触をいただくとともに、堆肥分析では全ての項目を網羅しようとすると新規の機器導入が必要となるといった意見もいただきました。
現在、農業技術センターでは水稲での可給態窒素に応じた窒素施肥の研究に取り組んでおり、将来、この可給態窒素が分析項目に採用されることが期待されます。
(土壌化学部:和田)
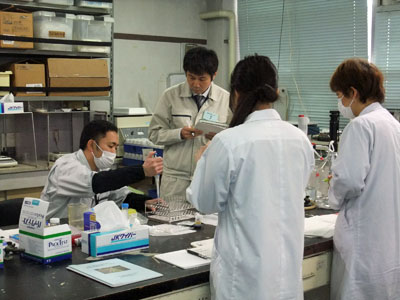
可給態窒素分析

堆肥分析
試験研究成果検討会を開催しました(2月17日)
農業技術センター「平成28年度試験研究成果検討会」を当センター講堂にて開催しました。「トマト独立ポット耕」50tどり技術、カキの品質保持技術、大豆の帰化雑草対策、コムギ縞萎縮病対策技術、果菜類ウイルス病の簡易診断技術、フランネルフラワー新品種のブランド化の取り組みの6つの研究成果(農業経営課1課題含む)を発表しました。
また、別の会場ではイチゴ新品種の試食や、試験成果のパネルおよび実物の展示も実施しました。
各地域の生産者、JA・市町・農業普及課職員など約100名の参加があり、成果の活用方法や普及上の問題点、試験への要望等について多数の意見をいただきました。
成果の普及については関係機関と連携・協力しながら迅速に行うとともに、いただいた意見を参考に研究開発や技術支援を進めてまいります。

センター所長あいさつ

研究成果の発表

試食、パネルによる研究成果の紹介

試食、パネルによる研究成果の紹介
水田土壌可給態窒素の簡易・迅速評価法の研修を行いました(12月7日)
県では県産米競争力強化推進事業を実施しており、県産米の市場評価を高めるべく高品質米生産の推進に取り組んでいます。各地域の実証水田の可給態窒素を把握した上で、それぞれの実証での品質や食味等への影響を評価するため、昨年度に引き続き可給態窒素の分析研修を行いました。今年度は、新たに開発された可給態窒素の簡易・迅速評価法による分析を行い、当センターの研究員の指導の下、15名の普及指導員等関係機関の職員が分析を体験し、簡易・迅速評価法の手法や可給態窒素を把握することの意義について理解を深めました。現在、当センターでも可給態窒素に応じた適正窒素施肥の研究に取り組んでおり、お互い連携しつつ進めていきたいと考えております。
(土壌化学部:和田)


葉菜類におけるリン酸減肥指標について講演しました(11月30日)
平成28年度関東地域マッチングフォーラム「土壌蓄積養分と地域資源の利用による施肥コスト削減」が開催され、農業生産者・団体、民間企業、試験研究・普及機関等の関係者ら約150名の参加がありました。本フォーラムは生産現場の方々と研究者が双方向に情報交換を行い、研究成果の迅速な普及・実用化を促進することを目的として開催され、講演やパネルディスカッション、成果の展示が行われました。当センターからは「コマツナ・ホウレンソウでのリン酸減肥」として、設定した葉菜類におけるリン酸減肥指標の概要と生産現場での普及状況について講演しました。講演後には多数の質問が寄せられ、適正施肥や施肥コスト低減への関心の高さが伺われました。
(担当:土壌化学部 和田)


「ぎふフラワーフェスティバル2016 in 花フェスタ」で育成品種を展示(11月11~13日)
花と緑のある暮らしを推進するためのイベント「ぎふフラワーフェスティバル」が11月11日(金)~13日(日)の3日間、花フェスタ記念公園で開催されました。本イベントでは、花飾り体験コーナー、花の即売会、プロの技を目の前で見るフラワーデモンストレーション、花いけバトル 等、園内で様々な催しがありました。当センターも「かれんシリーズ」の他、育成品種を多数展示しました。多くの方々に当ブースをご見学いただきました。


岐阜農林高校生の課題研究を支援しました(11月16日)
岐阜農林高校環境科学科の3年生の生徒4名が来所し、土壌分析を行いました。課題研究「淡水二枚貝飼育実験」でタナゴの繁殖に欠かせない二枚貝の生息環境を調査しており、対象としている二枚貝が生息する河川の底土について、昨年に引き続き調べたいとの相談がありました。そこで、河川の底土に含まれる様々な成分についての抽出や測定方法について説明をし、実際に分析を行ってもらいました。使用したことのない器具や経験のない操作に戸惑いながらの作業でしたが、真剣に取り組んでいました。研究課題が実りある成果につながることを、祈念しています。

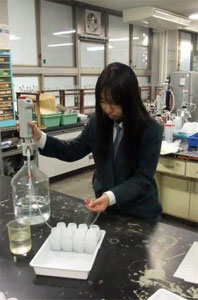
堆肥を原料にした肥料の開発について講演しました(11月10日)
国立研究開発法人 農研機構が主催し毎年、家畜ふん尿処理利用研究会が開催されています。本年は「家畜ふん堆肥の肥料利用促進に向けた課題と技術開発」をテーマに開催され、畜産業や肥料、資材関係の企業や団体、研究者など130名の参加がありました。当センターから講師に招かれ、豚ぷん堆肥を原料にした粒状肥料の開発事例について、開発の経緯や普及状況などについて講演を行いました。また、講演後にパネルディスカッションも行われ、活発な意見交換が行われました。堆肥の肥料原料としての利用は始まったばかりですが、今後、新たな耕畜連携の取り組みとして活発になることが期待されます。
(担当:土壌化学部 棚橋)
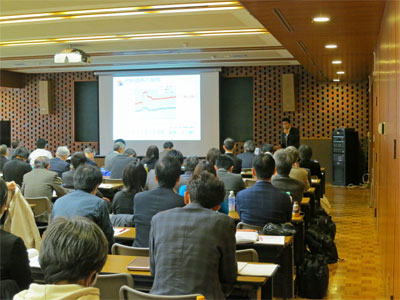
「第30回岐阜県農業フェスティバル」で研究成果を紹介しました(10月22~23日)
県農業フェスティバルが県庁周辺を会場として開催され、多くの方が来場されました。OKBぎふ清流アリーナ内「明日の農業コーナー」において、当センターからは化学合成農薬に替わる害虫防除技術(天敵ギフアブラバチとバンカー法による利用技術)や、堆肥を原料にした新規肥料を展示しました。
アブラムシの天敵であるギフアブラバチの展示では、大型ルーペを使って生きた実物が観察できる体験を行い、子供たちが多数観察しました。この展示の前では担当研究員が訪れた方にわかりやすく展示内容等、研究成果の紹介を行い、大変盛況でした。
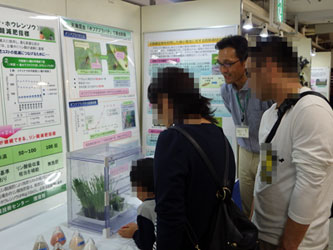

ベトナムゲアン省農業農村開発局より2名が来所されました(9月29,30日)
岐阜県とベトナムゲアン省は平成27年11月に友好交流に関する覚書を締結しており、農業や観光などの分野で交流を進めていく予定です。来年度に岐阜県の農業技術や政策を学んでもらうための研修が計画されており、今回はその事前調査のため農業農村開発局 栽培・植物保護部門の2名が岐阜県を訪れました。当センターでは本所と池田試験地において各分野の試験の内容や施設を視察されました。日本の先進的な生産施設や安全安心をテーマとした農産物生産への関心が高く、熱心に質問があり充実した意見交換となりました。
次年度からの研修を含めた交流事業が実りあるものになることが期待されます。


イチゴ「華かがり」の特性について講演しました(7月27日)
岐阜県園芸特産振興会主催の岐阜いちご生産者研究大会が山県市「文化の里 花咲きホール」にて来賓、いちご部会員、関係機関等、約300名の出席のもと開催されました。
研究大会の講演において、当センターが育成し、品種登録出願中のイチゴ「華かがり」の特性について情報提供を行いました。「華かがり」については本年作から現地実証試験を拡大し、約60a(生産者10名)にて栽培、販売を実施する計画となっています。「濃姫」、「美濃娘」に続く3番目の「岐阜いちご」として、生産者、関係機関一丸となってブランド化を目指します。
(担当:野菜・果樹部 菊井)

水稲品種「ハツシモ岐阜SL」の育成の経過について講演しました(5月23日)
当センターが平成23年に育成し、本県で最も作付けの多い水稲品種である「ハツシモ岐阜SL」の育成の経過について、理科の授業で遺伝について学んでいる岐阜市立東長良中学校の3年生約40名に講演しました。
遺伝的な側面からみた「ハツシモ岐阜SL」の育成について説明のリクエストがあり、「ハツシモ岐阜SL」の育成に使われた育種理論や遺伝子マーカーを利用した選抜技術などの説明を行いました。
(担当:作物部 荒井)
コマツナの土壌中リン酸含量に応じた減肥手法について講演しました(4月19日)
小松菜、水菜、小ネギなどの施設葉物産地である神戸町下宮地域の生産農家で構成される下宮青果部会協議会の総会がJAにしみの神戸集出荷センターにて開催され、協議会会員やJA担当者、西濃農林事務所農業普及課など約80名が参加されました。
総会後の基調講演において、当センターが設定した「葉菜類(コマツナ・ホウレンソウ)におけるリン酸減肥指標」について、下宮地域の施設土壌の化学性の現状から見た活用方法を中心に講演しました。下宮地域の施設では土壌中のリン酸が過剰に蓄積している傾向にあり、土壌や家畜ふん堆肥に含まれるリン酸を有効に活用することで施肥コストの低減につながることを説明し、リン酸減肥への理解を深めていただきました。
(担当:土壌化学部 和田)

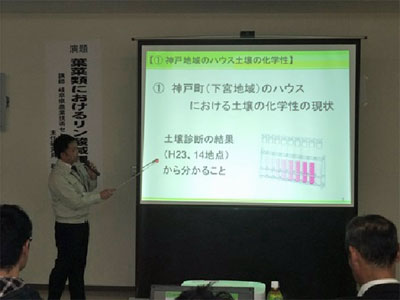
葉菜類のリン酸減肥指標について講演しました(4月15日)
関東東海地域の土壌および肥料に関する研究者、技術者、生産流通関係者で構成される関東東海土壌肥料技術連絡協議会の春季研究会が東京都千代田区、コープビルにおいて開催され、協議会会員など約70名が参加しました。
昨年度の関東東海・土壌肥料部会推進会議において、当センターにて設定に取り組んだ「葉菜類(コマツナ・ホウレンソウ)におけるリン酸減肥指標」が部会の「イチオシ」成果として選定されたことを受け、今年度の春季研究会において、減肥指標の設定経過や現地への普及状況などについて、これまでの成果を紹介しました。参加者からの指摘事項を踏まえ、生産現場へのリン酸減肥指標の普及をさらに進め、施肥コストの低減に貢献していきたいと考えています。
(担当:土壌化学部 和田)
