平成25年度イベント報告
関西茶業品評会に向けた茶園管理を支援(3月14日)
揖斐川町の現地茶園において、技術検討会が開催されました。生産者、役場、農協、農林事務所の関係者等で茶園を巡回して茶樹の生育状況を確認し、今後の管理について検討しました。農業技術センターからは茶担当の研究員が茶園管理のポイントについて助言しました。今後は、茶の生育にあわせた検討会を継続的に開催し、上位入賞にむけた取り組みを強化することとなりました。

東海地域農業関係試験研究機関連携による「統計研修」を開催しました(3月5~6日)
東海4県(静岡・愛知・岐阜・三重)の農業系研究機関連携協定の人材育成研修として「統計研修」をふれあい福寿会館で開催しました。(独)中央農業総合研究センターから講師を招き、愛知、静岡、岐阜の各県から19名の研究員の参加があり、当センターからも10名参加しました。研究データの解析に必須である統計処理の基礎と応用について詳細な講義を受け、熱心な質疑応答がなされました。
受講した研究員は今後の業務におおいに参考になったと感想を述べていました。


シクラメン生産者に葉腐細菌病の防除対策について講演しました(3月4日)
恵那花き研究会シクラメン勉強会が恵那総合庁舎で開催され、シクラメン生産者、普及担当者などを対象に、葉腐細菌病の防除対策について当センターの研究員が講演しました。勉強会では、診断技術や肥培管理、効果的な消毒方法について紹介するとともに、それらをまとめた防除対策マニュアルを配布し、情報交換を行いました。生産者の期待も大きく、消毒の方法の注意点など質問や意見が出されました。
当センターでは今後も関係機関と連携しながら、安定生産にむけたサポートを行っていきます。

薬剤耐性菌の発生状況と対策について講演しました(2月28日)
東美濃夏秋トマト生産協議会の栽培研修会がJAひがしみの本店(中津川市)で開催され、約80名のトマト生産農家の参加がありました。研修会では、当センター研究員が現地で問題となっている灰色かび病や葉かび病の薬剤耐性菌の発生状況についての情報提供と防除対策について講演し、ディスカッションしました。効率的な病害防除の必要性等について認識を深めていただきました。

小麦「さとのそら」の特性と栽培技術について講演しました(2月28日)
平成25年度麦・大豆生産振興研修会が農協会館で開催され、水田農業の担い手である営農組合や農家、JA担当者、普及指導員など約80名の参加がありました。研修会では、当センターの研究員が「さとのそら」の品種特性にあわせた栽培技術について説明しました。県では平成29年度から本品種の本格導入を目指しており、当センターでは実需の要望に応えた収量・品質向上に向けて、取組の支援を強化していきます。

関西茶品評会にむけた茶研修会で講演しました(2月27日)
平成27年度に岐阜県において関西茶業振興大会が開催されることとなり、そのメイン事業である品評会にむけて、揖斐川町をはじめオール岐阜県の茶農家、行政、農協等の取り組みを強化していくこととなりました。この強化策の1つとして2月27日に揖斐総合庁舎で「美濃いび茶振興会研修会」が開催され生産者、関係機関から約40名の参加がありました。この中で当センターの研究員が「上位入賞を目指す出品茶づくり」と題して講演しました。
農家や関係者一丸となり品評会の成功を目標に協力していくことで意識統一が図られました。

試験研究成果検討会を開催しました(2月20日)
農業技術センター「平成25年度試験研究成果検討会」を当センター講堂で開催しました。当センターが共同で開発したカキの重要害虫のカキノヘタムシガに対する交信かく乱剤(平成25年12月農薬登録)、カキの果実肥大予測、企業と共同開発した豚ぷん堆肥を活用したリサイクル肥料、黄色系フランネルフラワーの新品種育成、アザミウマの侵入を抑制する赤色ネット等、9つの研究成果を発表しました。また、別の会場ではお茶およびイチゴ品種の飲み・食べ比べや試験成果のパネルおよび実物展示も実施しました。
各地域のJA・市町・農業普及課職員など約100名の参加があり、成果の活用方法や普及上の問題点、試験への要望等について熱心に討議しました。
成果の普及については関係機関と連携・協力しながら迅速に行うとともに、今後も地域に根ざした研究開発や技術支援を進めてまいります。

矢野所長あいさつ

研究成果の発表

お茶品種の飲み比べ
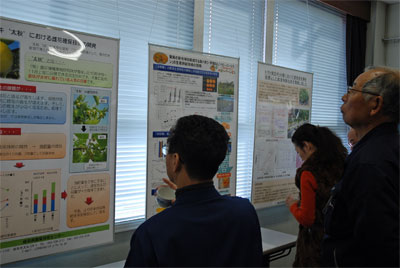
パネルによる研究成果の紹介
岐阜農林高校の校外研修を行いました(12月12日)
岐阜農林高校の園芸科学科1年生(40名)が12月12日、当センターに来所しました。これは岐阜農林高校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環で「農業の先端的研究」をテーマに校外研修として訪れたものです。
当センターの研究員が、開発した研究成果を交え、センターの業務概要等を説明し、実験室、ほ場の見学を行い質疑応答をしました。
園芸科学科の他に生物工学科、動物科学科、流通科学科の1年生それぞれ40名が翌月に研修に来所する予定です。


「消費者の部屋」で研究成果を紹介(11月26日)
農業技術センターおよび中山間農業研究所で開発した研究成果について「明日の岐阜県農業のために」をテーマに東海農政局(愛知県名古屋市)の「消費者の部屋」で紹介しています。
当センターからはトマトの独立ポット耕、カキの農薬飛散に配慮した省力防除技術、「ハツシモ岐阜SL」、フランネルフラワーの育成品種などの研究成果パネルと実物を展示しています。
東海地域の多くの皆様方に岐阜県の農業研究成果を知って頂ければ幸いです。


「いい夫婦の日フェア」で展示を行いました(11月16~17日)
「いい夫婦の日に花を贈ろう!フェア」が、11月16~17日にモレラ岐阜で開催されました。11月22日に花を贈るキャンペーンは、2009年に、いい夫婦の日に感謝を込めてバラの花を贈ろうと提唱されたのがきっかけです。
当センターからは、育成したフランネルフラワー、かれんシリーズ、サルビアの展示と紹介を行いました。訪れた方々は、鉢を手に取ったり、匂いをかいだりと大変興味深くご覧になっていました。
ご来場の多くの皆さんにお立ち寄りいただき、心より感謝いたします。


農業を学ぶ校外学習で小学生が来所しました(10月25日)
木之本小学校3年生33名が「岐阜市の農業を学ぶ」の一環で農業技術センターに10月25日に来所されました。
講堂でセンターの仕事内容についてのお話しと施設やほ場の見学をしました。中でも農業機械には興味津々で間近に見る機会が少ないためか、その大きさ、形に驚いていました。
あいにくの雨での見学でしたが、児童の皆さんは元気いっぱいで、担当研究員に手を挙げて、大きな声で返事や質問をしていました。


東海地域農業関係試験研究機関連携シンポジウムで展示を行いました(10月17日)
本シンポジウムは、東海4県(静岡・愛知・岐阜・三重)の農業系研究機関の効率的な技術開発や人材育成を図ることを目的とした4県連携協定の一環として開催しています。
今回は、農業の6次産業化をテーマに三重県で開催され、一般の方を含め100名を超える参加者がありました。シンポジウムでは基調講演や各県の事例紹介の発表を行ったほか、新品種・素材・試作品の展示を行いました。当センターからは、新品種として、水稲の「ハツシモ岐阜SL」、鉢花のフランネルフラワーを展示しました。次年度は、岐阜県で開催される予定です。


日本バイオロジカルコントロール協議会の方々が現地視察で訪れました(10月11日)
日本バイオロジカルコントロール協議会現地視察で生物防除資材の研究・開発、普及・販売をする方々50名が来所されました。アメリカシロヒトリ等の害虫に対する天敵微生物を利用した生物防除資材、トマトのポット耕栽培等、当センターの研究・成果の紹介と研究についてのディスカッションをしました。
やはり天敵微生物を利用した生物防除資材について関心が高く、生産過程、効果等、多くの質問がありました。


中国江西省花き協会リーダー候補生の方々が訪問されました(10月8日)
岐阜県と中国江西省は、本年、友好提携25周年を迎え、両県省関係者の相互訪問等の記念事業を行っています。今回、さらなる人的交流を拡大する観点から、江西省花卉協会(生産企業)のリーダー候補生3名が、本県の花きにおける研究開発を学ぶため、当センターを訪問されました。先進的な栽培施設を駆使した切花・鉢花生産での研究的課題やその解決技術について説明しました。ドライミストやLED等の環境制御システムに関心を示され、多くの質問を頂きました。


農業施設学会の若手研究員の方々が現地視察で訪れました(8月28日)
農業施設学会が岐阜大学で開催され、学会の現地視察で全国各地からの若手研究員・学生の方々15名が来所されました。岐阜県の農業、当センターの研究・成果の紹介と研究についてのディスカッションをしました。
岐阜県方式のイチゴ高設栽培やトマトのポット耕栽培の養液栽培方式についての関心が高く、多くの質問がありました。


岐阜農林高校インターンシップ(就業体験)受け入れ(7月22日~8月2日)
夏休みを利用して、岐阜農林高校生物工学科2年の学生10名が2グループに分かれて5日間ずつ来所し、作物部、花き部、野菜・果樹部、環境部、生物機能研究部で、それぞれ就業体験をしました。普段農作業の機会が少ない学生達は猛暑の中、慣れない管理作業や調査に戸惑う姿もみられましたが、体験を通じて仕事の厳しさ、やりがいが理解できたといった感想をいただきました。


トルコギキョウ、フランネルフラワー栽培研修会が開催されました(7月30日)
美濃地域でトルコギキョウと切花フランネルフラワーを栽培している生産者を対象とした栽培研修会が、当センターで開催されました。当センターからは、トルコギキョウの育種の状況や栽培状況、フランネルフラワーの栽培状況や現地試験について担当職員が説明しました。ほ場での検討と室内での意見交換が行われ、各生産者の現状とその対応方法等の質問や要望など活発な意見交換となりました。
当センターでは、今後もこのような活動を通じて花きの生産を支援していきたいと考えています。


農業大学校の学生が研修に来ました(7月16日)
農業大学校1年生の校外学習として、当所の研究概要を学ぶ研修会が開催されました。センターの研究概要の講義の後、米の食味試験、病害虫診断、堆肥の分析方法、野菜・果樹の栽培試験、作物・花き・イチゴの育種等について、ほ場視察を行いました。
普段経験できない内容が多く学生達には好評で、農業大学校で実施している「プロジェクト学習」で疑問に思っていることなどについて積極的に質問したり、メモを取ったりして熱心に研修を受けていました。
この中から、岐阜県農業の明日を担う農業者が誕生することを願っています。


いちご新規就農予定者に病害虫防除について講義しました(6月12日、27日)
JA全農岐阜のいちご新規就農者研修施設(岐阜市)で学んでいる研修生を対象に、病害虫防除について講義しました(6月12日:害虫、27日:病害)。当センターから虫害、病害それぞれの担当職員がいちご栽培を始めるにあたって問題となりやすい病害虫の見分け方や防除の考え方、ポイントなどについて紹介しました。研修生の関心は高く、ハダニの被害を早期に発見するコツや耐性菌を発達させにくい薬剤の選定方法などについて質問がありました。
当センターでは、今後もこのような活動を通じて新規就農を支援していきたいと考えています。

キュウリのミナミキイロアザミウマ防除について講演しました(6月20日)
海津胡瓜部会の全員研究会・栽培反省会が、JAにしみの海津営農センターで開催され、冬春キュウリ生産者、全農、JA、普及担当者など、約40名の参加がありました。
研究会では、近年問題となっているキュウリ黄化えそ病について、その媒介者であるミナミキイロアザミウマに対する赤色ネット被覆の侵入抑制効果などの研究成果を紹介しました。この赤色ネット被覆については、生産者の関心が高く、侵入抑制の仕組みなど多くの質問がありました。
当センターでは、今年度もキュウリ黄化えそ病対策としてアザミウマ防除の課題に取り組んでおり、効果的な防除技術について研究中です。今後も、各関係機関と連携しながら、生産者を支援していきます。


トマト主要病害の発生状況と防除対策について講演しました(6月11日)
県園芸特産振興会夏秋トマト部会中央研修会が白川町で開催され、夏秋トマトを栽培している各地域の生産農家の代表者やJA担当者、市場関係者や普及指導員など約80名の参加がありました。研修会では、現地で問題となっているトマトの灰色かび病や葉かび病の薬剤耐性菌の発生状況と対策、青枯病やかいよう病などの対策について防除のポイントや最新の研究状況について紹介し、効率的な病害防除の必要性等について認識を深めていただきました。

東海地域イチゴ担当者技術交流会を開催しました(6月6日)
当交流会は、東海4県連携協定の一環として静岡、愛知、三重、岐阜の研究機関と(独)野菜茶業研究所のイチゴ担当者が集まり、連携研究の模索や情報交換を目的に4県持ち回りで毎年開催されています。
本年度は当センターが主催、会場となり、16名の出席がありました。
会では、各研究機関の研究課題、成果等や今後の連携について意見交換を行った後、当センターの施設や栽培状況について説明しました。
当センターの取り組みについていただけた様々なご意見、また他機関の取り組みを参考に、今後も東海4県の研究機関の連携を密にしながら岐阜イチゴに貢献できる研究に取り組んでいきます。
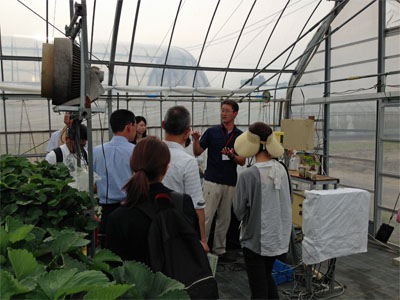
ボランティアで清掃活動をしました-ごみゼロ(530)の日にちなんで-(5月30日)
就業時間後に、農業技術センター、農業経営課、病害虫防除所の職員が全員参加してセンター周辺道路の清掃ボランティア活動を行いました。
この活動は数年前より「美しいふるさと運動」の一環で行われています。年々集められるゴミの量が減ってきています。特に住宅地でのゴミは少なく、住民の方々の美化意識の高さを感じることができました。今回の活動にとどまることなく、住民の方々と同じ意識を持って、センター周辺の美化に取り組んでいきたいと思います。

美濃市花とリサイクルを進める市民協議会総会で記念講演を行いました(5月29日)
美濃市では、市民総参加により花とリサイクルを進める市民運動を推進するため、市民協議会が組織されています。美濃市からの要請があり、出前講座の一環として、本協議会の総会における記念講演の講師を務めました。講演では、「ぎふ清流国体を盛り上げた花たち」と題して、フランネルフラワーの品種や栽培法、推奨花による国体会場の花飾りの様子などを紹介しました。参加した約100名の市民の方々は、国体を美しく彩った花たちの紹介に熱心に耳を傾けて頂きました。

「歩こう会」の皆さんが見学に訪れました(4月19日)
歩こう会は、ウォーキングを通して、地域の60~70歳代の方々が、親睦を深めることを目的に活動されています。今回、40名の会員の皆さんが、ウォーキングの目的地の一つとして、当センターを訪問されました。
見学では、研究員が花きの栽培施設で研究内容について紹介し、開花中のフランネルフラワーやキンセンカの「かれんシリーズ」を楽しんでいただきました。

